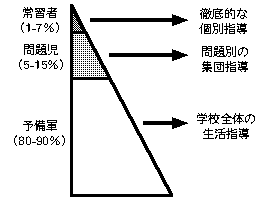
ワークショップ:問題行動に学校全体で取り組むために |
いじめや不登校、学級崩壊などの問題は、もはや、一人の教師やカウンセラーの努力だけで解決できるものではありません。学級や学年を越え、さらには保護者や地域も巻き込んだ、全体的な取り組みが必要とされています。
このワークショップでは、オレゴン大学を中心に結成されている、Center on Positive Behavioral Interventions & Supports(問題行動へのポジティブな介入と支援のためのセンター)の実践や研究をご紹介し、学校が抱える問題を全体的に取り組むための方法を模索します。
Positive Behavioral Interventions and Supports は、行動分析学の教育実践研究に基づいたプログラムで、学校の環境を整備して、子どもの望ましい行動を増やし、望ましくない行動を減らすアプローチです。ここでは、以下、PBISと略記します。
いじめや不登校、学級崩壊などの問題解決が難しい一因として、複数の原因が複雑に絡み合っていることが考えられます。
たとえば、問題の背景には次のような原因があるかもしれません。
テレビドラマのように、一人の教師が、その熱意だけで、こうした複雑な問題を解決していくというのは、あまりに現実からかけ離れていると言わざるを得ません。
問題解決の糸口は、コラボレーション、つまり、関係する人すべての協力にあるのです。
『80:20の法則』をご存じですか? 研究によれば、学校における問題にもこの法則がだいたい当てはまることが分かっています。つまり、80%の問題は、20%の子どもが引き起こしているということです。単純に計算すれば、30人のクラスでは、6人が「問題児」ということになりますね。
「問題児」のうち、問題行動を繰り返す「常習者」は、さらにその一部です。研究から「常習者」は全体の1-7%だとされます。つまり、30人のクラスで「常習者」は多くても1-2人ということになります。
「問題児」とか「常習者」という言葉は、子どもにレッテルを貼るために使っているわけではありませんので、誤解しないで下さい。ここで重要なのは、解決すべき問題の原因と対策を探るために、問題がどこにあるかをまずは見極めることです。
米国の学校では、「Office Referral」という手続きがよく取られています。これは、暴力や遅刻、さぼり、いじめなどの問題を起こした子どもを、生徒指導の先生や、教頭・校長の部屋に呼び出して、指導するという手続きです。どんな問題行動が、どこで、いつ、誰に対して発生したかを、書類として残すので、問題児や常習者が誰か、どんな問題が、どんなふうに発生しているのかを、比較的、客観的に捉えることができます。こうした手続きは、教師の思い込みや個人的な感情によって、子どもへの対応にバイアスがかからないようにするために重要だと考えられます。
もちろん、「問題児」や「常習者」以外の子どもには何もしなくていいわけではありません。80%の子どもは、ある意味で、「問題児」予備軍なのです。「問題児」の影響を受けて、問題児化する子どももいるでしょう。近頃、マスコミで報道される事件では「普段は大人しい子だったのに」とか「あの子があんなことをしたとは未だに信じられない」などというコメントが発表されることがあります。「予備軍」も十分にケアしないといけない証拠です。
PBISでは、子どもをおおまかに3つのグループに分けて、それぞれ別の対処をします。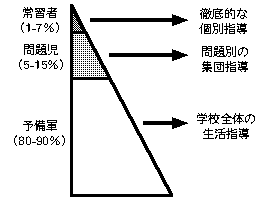
常習者に対しては、徹底的な個別指導を組みます。問題児に対しては、問題行動ごとにプログラムを組んで、それを該当する小集団に実施します。そして予備軍に対しては、学校全体による生活指導(School-Wide Classroom System)で対応します。
図は、Lewis, T. J., & Sugai, G. (1999). Effective Behavior Support: A Systems Approach to Proactive School-wide Management. Focus on Exceptional Children, 31(6), 1-24. より、著者の許可により転記。
基本的に、行動分析学では、問題行動の原因が、問題を引き起こしている本人の性格とか能力、態度などにあるとは考えません。そう考えても、問題の解決には一歩も近づけないからです。
その代わり、行動分析学では、(1)問題行動がどのような環境によって引き起こされているのか、(2)環境をどのように変えれば行動が変容するのかを考えます。これが機能分析です。機能分析については別のワークショップを準備中です。ここでは詳しく説明しませんが、一つだけ例をご紹介します。
たとえば、授業中、大声を出したり、隣の子どもにちょっかいを出す児童の行動の原因を「落ち着きがないから」とか「キレやすいから」と考えても、問題解決には結びつきません。機能分析では、このような問題行動と、その前後の環境を観察し、どのような条件で問題行動が起きやすいか、何がきっかけになっているか、どのような結果が問題行動を強化しているかを推測します。
下の図では、行動に影響を及ぼす要因を、「確立操作」(たとえば、頭痛があるときに大声を出しやすい)、「先行条件」(たとえば、隣に仲の良い友達が座るとちょっかいを出しやすい)、「自然的結果」(たとえば、大声を出したり、ちょっかいを出すと、先生や友達から注目を得られる)というように分析しています。
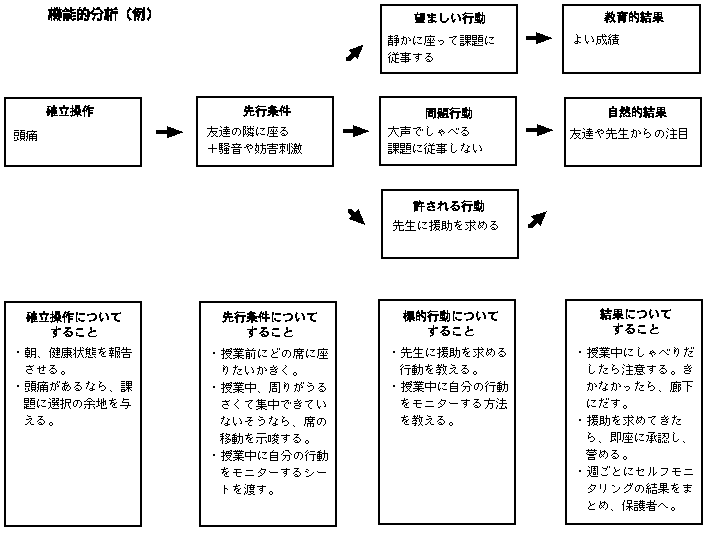
*図は、Sugai, G., Lewis-Palmer, & T., Hagan (in preparation) Using functional assessment to develop behavior support plans. より、著者の許可で転載。
機能的分析によって、何もしないでそのままにしておくと問題行動が強化され続けるということが分かったら、環境を変えて、問題行動が起こらないように工夫します。これを介入と言います。介入には、問題行動が生じてしまってからの対処的介入と、生じる前に行う予防的介入があります。学校全体で問題行動に取り組むPBISでは、この両方の手続きについて、すべての教員が共通の認識を持ち、子どもに対して一貫した手続きをとることが前提になります。先生によって問題行動への対処が異なると、子どもは混乱し、行動は改善されません。
上の例では、対処的介入として、授業中にしゃべりだしたら、まず注意すし、それでも聞かなかったら廊下に出すという手続きが決められました。PBISでは、こうした手続きが、教員の代表者会議(「常習者」の場合、その子どものケース会議、「問題児」の場合、問題行動ごとの対策会議など)によって決められて、教員全員に告知されます。もちろん、子どもや保護者にも知らせます。算数の先生は注意するけど、理科の先生はまったく注意しないということになれば、子どもは、当然、理科の時間にしゃべりだします。大切なのは環境の一貫性なのです。
望ましくない行動をいかに減らすかが対処的介入だとすれば、望ましい行動をいかに増やすかが予防的介入です。
これまで、たとえば、授業が始まったら席に座って教科書を開く、先生には敬語を使い、指示に従うなどは、できてあたりまえの行動でした。ところが最近では、この常識がもろくも崩れ去っているといいます。でも、だからといって、下の学校(高校なら中学、中学なら小学校)が悪いとか、家庭に問題があると責任転嫁しても、問題は解決しません。
今や、できてあたりまえの行動をわざわざ教えなくてはならないという現実を直視するしかありません。なぜなら、それなしでは授業が成立しないからです。
PBISでは、できてあたりまえの行動を、まずは具体的に書き出して、学校全体で合意を得るところから始めます。子どもにどんな行動を期待するか、話し合ってみると、意外にも意見がバラバラであると分かるかもしれません。子どもに対する期待が一貫していなければ、子どもは混乱します。繰り返しますが、大切なのは教師も含めた環境の一貫性です。
下の表は、あるオレゴン州のある小学校で使われている「子どもへの期待」をまとめたものです。『自分を尊敬する』『友達を大切にする』『物を大事にする』という3つの理念を、学校の8つの場面ごとに、具体的な行動として書き表しています。
|
場 面 |
|||||||
| 期 待 |
すべての 場面で |
廊下で | 校庭で | 学食で | 図書室で | 体育館で | トイレで |
| 自分を 尊敬する |
・課題に集中する ・一生懸命頑張る ・次に何をすべきか気にする |
・静かに歩く | ・楽しむ ・規則を守る |
・健康的に食べる ・マナーを守る |
・静かにする ・勉強する、本を読む、コンピュータを使う |
・静かに座って待つ | ・手をよく洗い、乾かす |
| 友達を 大切にする |
・適切な言葉遣いで話す ・手や足で乱暴しない ・助け合い、分かち合う |
・お喋りしない ・静かに歩く |
・安全に遊ぶ ・仲間はずれにしない ・共有する |
・マナーを守る | ・ささやき声で | ・先生の指示をよく聞き、周りをよく見る ・友達を拍手する |
・備品を使う |
| 物を 大事にする |
・使った物は片づける ・物を壊さない |
・掃除をする | ・ゴミはゴミ箱へ ・道具は適切に使う |
・お盆はきれいに片づける ・食事が終わったらテーブルをふく |
・帰るときには椅子を元に戻す ・本やコンピュータは丁寧に扱う |
・マットや支柱を適切に扱う | ・備品を丁寧に使う ・掃除する ・節約する |
もちろん、こうした行動目的を紙に書き出すことは大切な第一歩ですが、それだけでは子どもの行動は変わりません。子どもの行動を変えるためには、望ましい行動が強化されるように環境を整備することです。
PBISでは、環境を整備するために様々な方法をとります。たとえば、新入生全員に対するガイダンスでは、学校の各場面で期待される行動について、次のようなトレーニングが実施されます。
他にも、子どもが望ましい行動に従事するのを継続的に動機づけるために、子どもが望ましい行動をしているのを見たら、教師はそれを当たり前のこととして無視せず、言葉やシールで誉めるようにします。
学校によっては、一日最低3枚はシールを配ること、と教師側に義務づけることもあります。当たり前のことを誉めるのは、なかなか難しいことです。言葉だけで誉めるようにすると、すぐに忘れがちです。シールを使うことは、子どもにとって教師から認められたことがはっきりするだけでなく、教師にとって子どもを誉めることを忘れなくするという働きがあるのです。
PBSIの学校全体による生活指導では、「校則」の見直しと、それに沿った一貫した指導を重視します。このとき、特に、問題行動の予防的介入から考えると、校則を破った子どもを罰するだけでなく、校則を守っている子どもを認めて、できるだけ頻繁に誉めることが重要になります。ここが、従来の校則の使い方(特に日本の学校の)とは、大きく異なる点と考えられます。
PBISは、オレゴン大学のホーナー博士やスガイ博士を中心としたチームが、米国教育省からの援助を受けて、推進しています。しかしながら、彼ら大学スタッフの役割は、あくまでコンサルテーションであり、プロジェクトを実施していく中心は、校長・教頭を中心とした学校の教師です。
スガイ博士によれば、プロジェクトが成功するかどうかは、(1)校長と教頭の間に信頼関係が形成されているかどうか、(2)それを中心に教師が協力体制を築くことができるかどうか、(3)保護者や地域の人々の賛同と協力を得られるかどうか、にかかっているそうです。このため、スガイ博士らは、教師や保護者への講習会の実施や、プロジェクトチームの運営、個別のチーム(たとえば、学年別のミーティングなど)のファシリテーションなどを支援しています。
実際に子どもと向き合うのは教師です。大学のスタッフは、教師の主体性を優先し、教師が仕事をしやすいように支援するという立場を守っているようです。PBISが軌道に乗ったら、大学のスタッフは徐々に手を引いていき、学校が自立して、PBISを継続していけるように、外からサポートしていくという方針です。
PBISは、これまで積み重ねられてきた応用行動分析学の教育実践研究をベースに開発されています。また、米国各地で導入されていくにつれて、その効果が実証されつつあります。
ここでは、いくつかの参考文献をご紹介します。これらの参考文献については、今後、『行動分析学の部屋』で解説をしていく予定です。