レポート:自閉症サポートの最先端−TEACCHプログラムに学ぶ(2) |
2002年9月14日から16日まで上越教育大学で開催された第40回日本特殊教育学会で、自主シンポジウム『自閉症サポートの最先端−TEACCHプログラムに学ぶ(2)−』に指定討論者として参加しました。ここではこのシンポジウムで学んだこと、考えたことについてまとめます。
まず、司会の梅永雄二先生(明星大学)からシンポジウムの主旨などについて説明がありました。梅永先生によると、「自閉症カンファレンス」という、TEACCHプログラムを実践している人たちが集まる会がたいへん盛況で、今年は参加者が1200人にも及んだそうです(希望者は2800人くらい)。参加者には、自閉症をもった人たちを支援する教師、施設職員、保護者の方々が多いそうです。自閉症の教育・福祉分野に、効果的な支援サービスに対する大きな需要があることがわかります。
『自閉症サポートの最先端−TEACCHプログラムに学ぶ−』というタイトルのシンポジウムは実は今年で2回目であり、梅永先生としては、特殊教育学会のようなアカデミックな場でもTEACCHプログラムに関する認識を広めたいという意向があるようでした。また、TEACCHプログラムの効果を科学的、学術的に検証したいということで、そのためには、多くの研究者にTEACCHプログラムを知ってもらい、その方法論などを研究として検討してほしい、という希望もあるようです。私のような“門外漢”を指定討論者に呼ぶのには、こうした目論見があるとのことです。
ちなみに、昨年のシンポジウムで指定討論者をお務めになった山本淳一先生(慶應義塾大学)からは、TEACCHプログラムにはその効果を客観的、実証的に示す研究が少ないこと、プログラムの改善に役立ちそうな最新のデータや研究を必ずしも活用しておらず、改善の余地があること、などが指摘されたそうです。
日本でTEACCHプログラムの先駆者的役割を果たしている方々には、確かに『研究』を本業としている人は少ないようです。前述の「自閉症カンファレンス」でも参加者の多くは実践家であり、事例報告は豊富でも、要因を統制して指導方法と指導効果の因果関係までを示すような研究は少ないようです。ですから、この部分には確かに改善の余地がありそうです。それでも、梅永先生を初めとして何人かの先生方が大学に所属されるようになり、また、このようなシンポジウムを継続していくことで、TEACCHプログラムの要素を実証的に検討するような研究がでてくればよいと思います。
さて、シンポジウムでは、予定されていた話題提供者のうち、安倍陽子先生(横浜南部地域療育センター)がご病気のため、急遽、古川宇一先生(北海道教育大学)がピンチヒッターに立たれたこと以外は順調に進みました。以下、各話題提供者のお話から、私の印象に残った点を、感想を含めてピックアップしました(各話題提供について詳しくは大会論文集をご覧下さい)。
TEACCHをどう生かしていくのか
坂井 聡先生(金沢大学大学院)
坂井先生は香川大学附属養護学校の先生で、現在は金沢大学大学院に内地留学されています。坂井先生は、自閉症をもった人たちそれぞれがどんな支援を必要としているのか、そのニーズを知ることが最優先であると話されました。“この子は自閉症だから、これこれこういうニーズがあるはず”と、支援する側が紋切り型で決めつけるのではなく、個々人の支援ニーズをしっかり把握することからすべては始まるということでした。
喩え話として、こんな話を紹介されました。
「盲の人がカメラ付き携帯電話が欲しいと言いました。どんなニーズがあるのでしょう?」
目が見えないのだからカメラ付き携帯はいらないだろうと考えるのではなく、どんなことで困っていて、どんなふうに支援できるだろうと考えていくと「文字などを映して電話の向こうの相手に読んでもらう」という支援方法が考えつくとのことです。
TEACCHの“信奉者”からは、「この子は自閉症だから視覚的刺激を使うべき」とか「この子は自閉症だから言葉がけはいっさいすべきでない」などの、極端な紋切り発言を聞くこともあます。これに関してはたいへん憂慮していました。ですから“自閉症だから”ではなく、個々人のニーズの把握を最優先するという坂井先生のスタンスには安堵感を感じました。
ただ、個々人のニーズをしっかり把握するにはかなりの力量が必要になります。坂井先生もご指摘していたように、教師の実践的な力量を底上げする研修が重要になってくるでしょう。
指定討論としては、このニーズの把握に関して一つ質問をさせていただきました。たとえば、音声による声かけを理解するのが難しく、でも文字カードなら指示が通りやすい子どもさんに対して、文字カードを支援していくというのは、ニーズも対応する支援もわかりやすく、実施しやすいと思われます。しかし、もしそのお子さんに、音声による簡単な声かけに適切に反応できるように教えることができたらどうでしょうか? そのお子さんの生活は格段に暮らしやすくなると思われます。
自閉症をもった人たち(に限りませんが)のニーズは、現状のスキルレベルでのニーズだけでなく、新しいスキル獲得の可能性も含めて捉えるべきではないだろうか?というのが私の質問でした。これに対して、坂井先生からは、少し違った角度からご回答をいただきました。坂井先生は、「シェフ」と「コック」というアナロジーを使って、教師のすべてをシェフとしてトレーニングすることはできないので、まずはコックとして十分に力を発揮できる人を育てるのが現実的な目標であるとされました。つまり、すべての教師がそこまでのニーズ把握とそれに対応した指導プログラムを考えられるようにするのは難しいので、まずは現実的な目標として、現状のスキルレベルでのニーズ把握だけでもしっかりできるようになりましょう、ということです。
TEACCHプログラムは時間の構造化(スケジュール)、場所の構造化、自立課題(ワークシステム)など、“型”ができているので、実践には移しやすく、その意味では「コック」さんを養成しやすいシステムになっていると思います。しかしながら、子どもが期待通りに動かなかったとき、一人ひとりの先生にできることは逆に限られてしまうようにも思えます。やはり“型”としての手続きだけではなく、なぜその手続きがうまくいくのか、うまくいかないときにはどんな原因が考えられるのかという“法則”とか“原理”の理解がないと、すなわち、坂井先生のいう「シェフ」としてのトレーニングが積まれないと、教えるという仕事を責任をもって遂行するのは難しい場合もでてくると思います。
坂井先生はご自身の実践として、TEACCHのアイディアをいくつかご紹介され、またAAC(代替的コミュニケーション)や、問題行動の原因を捉えて代わりに望ましい行動を教えることなどについて紹介されました。ちなみに、坂井先生はご自分の手帳にPECS(絵で様々な事柄を表現するシステムで、代替的コミュニケーションとして活用されている)を綴じてあり、道ばたで自閉症らしき人に会うとそれで話をしたりするそうです。
代替的コミュニケーションに関しては、応用行動分析学から数多くの研究が行われています。PECSもそもそもは応用行動分析学の研究者が開発したシステムです。また、問題行動と望ましい行動を置換する方法は、機能的アセスメントや分析を使った積極的行動支援(Positive
Behavior Support)として、行動分析学ではすでに常道になっています。少なくとも実践のレベルでは、TEACCHプログラムと応用行動分析学とはうまく融合して使われているんだなぁという印象を受けました。
ノースカロライナ州における青年以降の自閉症支援
服巻 繁先生(西南女学院大学)
服巻先生は昨年1年間ノースカロライナでTEACCHの研修を受けてこられ、現在は西南女学院大学で教鞭をとってらっしゃいます。タイトルにもあるように、話題提供では、ノースカロライナ州における青年以降の自閉症支援についてお話しされました。
印象に残ったのは、その柔軟性でした。日本では“TEACCH=カード”というイメージが先行していますが、服巻先生によれば、ご本人さんの行動レパートリーに応じて、手話を使ったコミュニケーション支援をすることもあるとのことです。
また、服巻先生が滞在されていたのが農村部であったこともあり、農業や、カニ漁のための罠を作る作業などを就労支援することが多かったようです。しかも、このカニ漁のための罠作りは収益を生んでいる事業だということでした。
実は、日本で先進的な取り組みをされている佐賀の朝日山学園を見学したとき、近くに田畑が多かったので、「農業関係の就労はどうなんでしょうか」とお聞きしたことがありました。これに対して、田中施設長さんからは、「自閉症の方は土をいじらせると感覚遊びになってしまうので、難しいですね」という答えをいただきました。もちろん個々人によって異なるでしょうが、自閉症をもった人たちでも農作業への就労を支援できるという事実、そしてその方法論がわかれば、日本でも農村部などでは役に立つのではないでしょうか。
指定討論では、ノースカロライナのシステムについて、自閉症に関する研究やその成果をプログラムとして開発する仕事はどこが担当しているのか、開発したプログラムを教師など、実践家にトレーニングする仕組みはどうなっているのか、についてお聞きしました。実は、この件に関しては、服巻先生に以前メールで質問したことがあり、そのときの回答が残っていますので、ここに要約して転記させていただきます。
Q:研究はどこが担当していますか?
A:Division TEACCH という組織が研究を担当しています。
Division TEACCHは、TEACCHプログラムを統括する組織で、メジボフ教授が部長です。その下に各地域のTEACCHセンターがあり、その長は所長です。Division TEACCHはノースカロライナ大学チャペルヒル校の医学部精神科に属する大学の組織です。
新しい教授法を開発するのは、Division TEACCHですが、その導入には幾つかパターンがあるようです。(1) Division TEACCHオリジナルで開発するもの、(2)
他所で効果的だと思われている指導法を取り入れる場合(最近のPECSなど応用行動分析学系が多い)、(3) 現場で効果的だと思われているものを取り上げる場合です。いずれも、現場で実際に試してみて、所長会議などで検討して導入を決めるようです。こうした研究の成果は、主にJournal
of Autism and Developmental Disabilitiesなどに発表しているようです。
研究も、指導法に限らず、疫学、遺伝、脳、神経生理学など広範囲です。医学関係は、医学部の先生などとコラボレーションしているようです。現在のDivision TEACCHの建物は、大学とは離れて、Division TEACCH、チャペルヒルTEACCHセンター、援護就労部、プリスクールの他に、自閉症の脳生理学研究を行う部門が一緒になったものです。
Q:実践家へのトレーニングは?
A:実践家へのトレーニングは、各地域のTEACCHセンターで行われるワークショップと、教育現場、施設現場での実地訓練を通して行われます。
大学内でのTEACCHプログラムに基づいた講座、授業とか訓練はありませんが、特殊教育教員養成では、応用行動分析学と共に自閉症には視覚的プロンプトによる支援というのが常識化しています。また、TEACCHで行っているサービス(CLLC、キャンプ、援護就労)などに、ボランティアやパート、研修という形で参加する学生(特殊教育、心理、ソーシャルワークなど)はいます。それらの情報はウェブ上に載っていたり、授業やゼミで先生が紹介したりするようです。
服巻先生のお話しからは、少なくともノースカロライナの現場では、自閉症をもった人たち個々のニーズ、個々の行動レパートリーにそくして、“カード”などに固執することなく、有効な方法論は取り入れた教育・福祉サービスが提供されているようです。
梅永先生が「TEACCHは“いいとこどり”と批判されることが多いんです」とおっしゃっていましたが、自閉症をもった人たちの生活の質が向上するのであれば、どんどん“いいとこどり”をすべきだし、ノースカロライナには、Division TEACCHとその下部組織、協力研究機関という形態で、そのようなシステムができているのだなぁと思いました。
それに較べると、残念ながら日本では、研究組織と実践家を結ぶこのようなシステムが弱いような気もします。このへんを補強していくのが梅永先生の狙いなんでしょうね。
北海道函館地区と旭川地区のTEACCHプログラム導入の試み
古川宇一先生(北海道教育大学)
古川先生は10年以上も前から北海道の函館と旭川で、地域に根ざし、生涯にわたったサポートシステムづくりに力を注いできたそうです。話題提供ではその歴史と現状についてお話しされました。
印象に残った点は、配付資料にもあったように「TEACCHプログラムは構造化のみではなく、生涯にわたる地域ケアの体制に学びたいように思います。極端な話、構造化でなくとも適切さと一貫性と継続性、連携性のある療育が地域にあればいいのである」という点です。
TEACCHの講習会などでは「TEACCHは方法論ではない。TEACCHはシステムなんです」という話を聞きます。服巻先生の話題提供でも改めて確認したように、ノースカロライナ州の元祖TEACCHは、行政機関が提供する包括的なサービスです。もちろん、個々の指導法には自閉性障害の特性をよく理解した上での工夫がたくさん見られますが、“いいとこどり”の話からもよくわかるように、必ずしもオリジナルブランドの指導方法にこだわっているわけではなさそうです。
ノースカロライナ州で自立して生活している自閉症の人の割合は8%(他の州では40-78%)と、たいへん低い数字を示しています。これは一つひとつの指導法による効果というよりも、古川先生が指摘するように、行政による支援体制の「一貫性」「継続性」「連携性」によるところが大きいのではないか、と思いました。
古川先生の配付資料には、函館と旭川の各地域、幼児期から高校卒業後までの各ライフステージにおける、TEACCHプログラムの普及度に関するデータがありました。たとえば、TEACCHプログラムを導入し始めた幼稚園がいくつあり、3年以上導入している小学校がいくつあり.....というデータです。
こうしたデータは指導方法の普及度を示すものですが、逆に言えばそれだけしかわかりません。指定討論では、TEACCHプログラムが導入されてどのような成果があったか、それをどのように確認しているか、という質問をしました。
たとえば前述のように、ノースカロライナの場合、地域で自立して生活している人の割合が調査されています。システムの評価にはこうした成果のデータが欠かせないと思っての質問でしたが、古川先生からは「これからの課題です」というご回答をいただきました。
これは私自身の研究テーマでもあるのですが、学校単位で一つの取り組みを始めた場合、その取り組みの効果をどのように測定し、評価できるだろうか、という課題です。
個別指導計画の達成度、本人、保護者、教師の満足度、行動的QOLの目安とされる選択機会の数、パニックを起こした回数、課題従事率、などなど、複合的な指標を使って学校のパフォーマンスを測定して、パフォーマンスを向上していくための取り組みを改善していく、という仕組みを作っていきたいと考えています。
福祉・教育支援サービスモデルとしてのTEACCH
島宗 理(鳴門教育大学)
最後に私の指定討論です。「TEACCHはシステムだ」ということですので、TEACCHを福祉教育支援サービスモデルとしてみた場合に何が学べるかという視点から、下の図を使って、すでに述べてきた質問をしました。
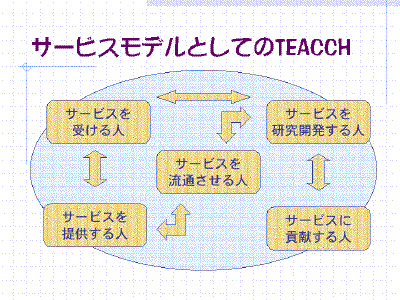
福祉・教育支援サービスモデルとしてみた場合、まず、サービスを受ける人たちがいて、この人たちのニーズがシステマティックに吸い上げられなければなりません。初めにニーズありきのスタンスの重要性とその難しさは、坂井先生とのやりとりの中にでてきたと思います。今後の課題になりそうです。
サービスを研究開発する人については、服巻先生のお話から、ノースカロライナではDivision TEACCHがメインに行っているが、“いいとこどり”にも積極的であるとのことでした。日本の場合、Division TEACCHにあたる組織はないわけなので、梅永先生の狙いのように、学会などを通して、研究者と実践家が情報を交換し、よりよい支援方法やシステムをつくるための実証的な研究が進めばいいと思います。
サービスを提供する人(教師、職員、保護者など)への研修、あるいはサービスを流通させる人たちの研修や登用の仕組みについても、本場と日本では大きく異なり、これからの課題がたくさんあるなぁと感じました。
そもそも私が個人的にTEACCHに興味を持ったのは、日本でTEACCHプログラムを実践している一部の方の指導方法や発言が、図書や資料で読む本場のTEACCHプログラム、あるいはノースカロライナで研修されてきた方の話と大きく異なることがあったからです。
おそらくは、サービスを研究開発する人から、流通させる人、そしてサービスを提供する人までの情報の流れ方が十分ではなく、また、サービスを提供する人が、じっさいにどんなサービスを提供して、どんな成果を上げているか、あるいは上げていないのかの情報が、逆方向に吸い上げられていないのではないだろうか?と考えていました。
服巻先生のお話では、ノースカロライナではTEACCHセンターからの指導者が学校にコンサルタントとして入って、教師に対し実地指導をしているとのことです。しかし、日本ではそもそもそうしたコンサルタントの数が限られており、また学校はその予算を独自に獲得しなければなりません。また、学校や教師によっては、そのようにして外部から教育に口をだす専門家を敬遠する文化もいまだに根強く残っていると思われます。
もちろん、こうした問題点はTEACCHプログラムに限らず、日本の教育・福祉サービス全体にあてはまることだと思います。この点では、古川先生の「TEACCHから学ぶこと」に私はまったく同感です。
私もここ数年間、地域の養護学校と共同で、教育サービスの質の向上に必要なシステムについての研究をしています。教員への研修、トレーニングの仕組み、最新の研究情報を流通させる仕組み、適切な指導目標を設定し、達成する仕組みなど、いくつかのサブシステムを連携し、その成果を確認しながら改善していく方法論の開発に頭を悩ませています。
日本における教育・福祉サービスシステムづくりの研究に取り組んでいく上で、TEACCHの本場、ノースカロライナ州のシステムに学ぶところは大いにあると思いました。
最後の最後に:
このシンポジウムは来年も継続して開催するとのことです。梅永先生が、山本先生や私のような行動分析家を指定討論者に呼ぶのは、ある意味で、『TEACCH
vs 応用行動分析』という“対立軸”を想定することでシンポジウムが盛り上がると考えていらっしゃるからかもしれません。シンポジウムの最後に、フロアーからは、もっと過激なやりとりを期待してたのにという感想も聞かれました。しかし、私は別のところ(行動分析学からみたTEACCHプログラム)にも書いたように、TEACCH
と 応用行動分析学の比較はナンセンスであり、較べる性質のものではなく、さらに無理矢理較べても生産的なことにはならないだろうと考えます。
今回、このシンポジウムに参加したことでこのことに関してたくさんの人たちと話をする機会に恵まれましたが、『TEACCH vs 応用行動分析』という“対立軸”を信じている人たちは、TEACCHか、応用行動分析学のどちらか、あるいはどちらもよくわかってない人たちのようでした。もちろん、TEACCHの研究者/実践家の一部の人
vs 応用行動分析学の研究者/実践家の一部の人、という“対立軸”は実在しているかもしれません。でも、それと『TEACCH vs 応用行動分析』とはまったく別の話ですよね。
自閉症をもった人たちの生活の質の向上という共通目標がある限り、どちらの考え方も、どちらでトレーニングを受けた人も、協働で取り組めるはずですし、すべきだと思います。
来年の指定討論は、『シンポジウムは格闘技である!』がモットーの(?)行動分析家が参加する予定だとお聞きしています。ただし、彼が言うように、格闘技は観客がルールを理解してこそ楽しめるものです。みなさん、ぜひ十分に予習をして来年のシンポジウムを楽しみに待ちましょう。